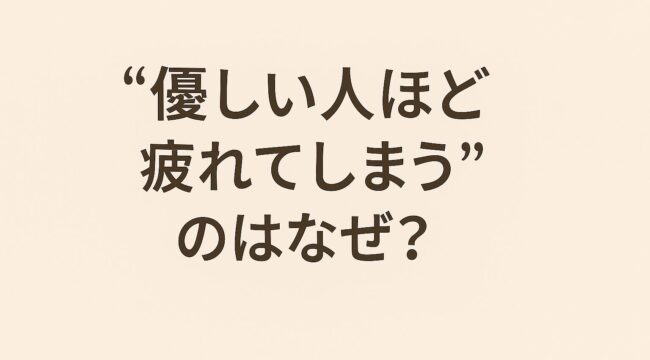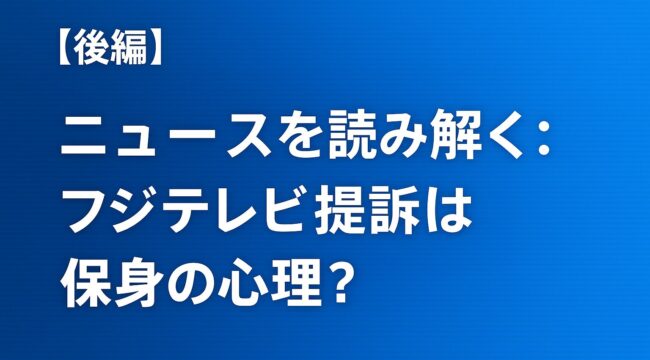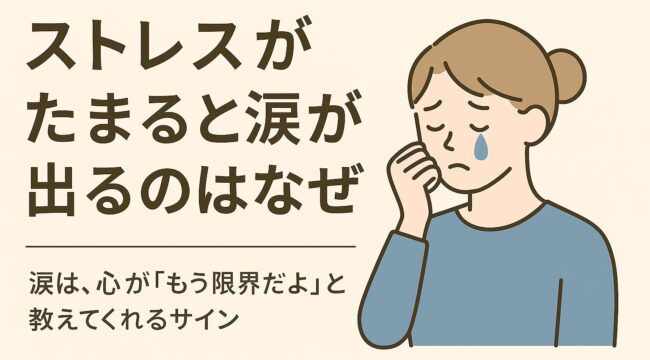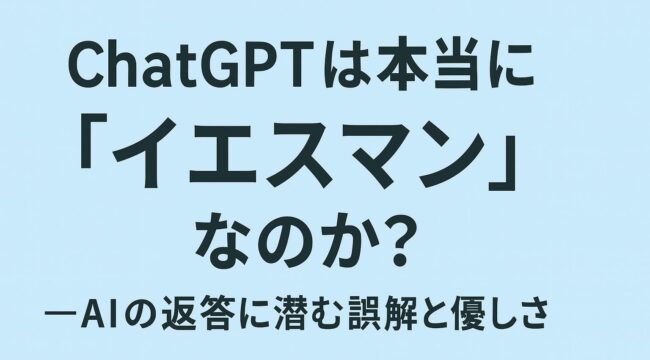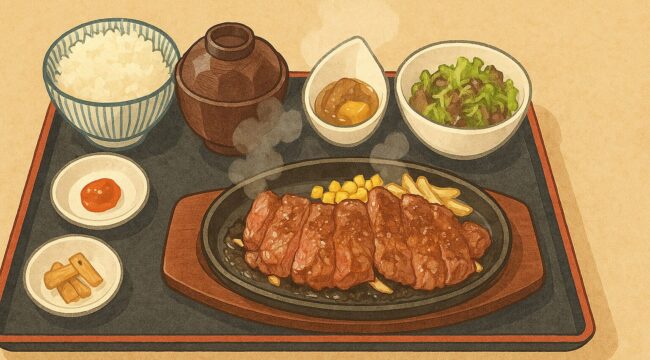フジテレビが港浩一前社長と大多亮元専務を相手に、50億円の損害賠償を求めて提訴したことが報じられました。
ニュースを見たとき、「フジテレビは前社長らを悪者にして、自分たちのメンツを守ろうとしているのでは?」と感じた方もいるのではないでしょうか。
企業不祥事にありがちなパターン
企業が不祥事に直面すると、いくつかの“あるある対応”が見られます。
- 個人に責任を集中させる
「特定の経営陣の問題」であり、会社全体は被害者だと位置づける。 - 形だけの謝罪や再発防止策
「深く反省しています」「再発防止に努めます」と言いつつ、実効性に乏しい。 - 毅然とした姿勢をアピール
訴訟や処分を打ち出し、「我々は正しく対処している」と外部に示す。 - 広報・会見で印象をコントロール
あたかも責任を果たしたかのように演出し、根本改革は後回しになる。
今回のフジテレビの提訴は、このうち 「個人責任の強調」と「毅然とした姿勢のアピール」 に当てはまるといえます。
メンツを守るアピールの側面
フジテレビが前社長らを提訴した背景には、
- 「問題を起こしたのは前経営陣」という構図づくり
- 「毅然と対応する会社」という姿勢の発信
といった“アピール活動”の意味合いが強いと考えられます。
しかし同時に、組織全体としてのガバナンス不備や体質の問題が見えにくくなり、
「本当は会社ぐるみだったのでは?」という不信感を逆に強めるリスクもあるのです。
本当に必要なのは「構造の変化」
一時的な責任追及だけでは、長期的な信頼回復は難しいでしょう。
求められるのは、
- 被害者への誠実な謝罪と救済
- 第三者委員会による調査と報告の公開
- ガバナンス体制の抜本的改革
- 経営陣全体としての責任の明確化
といった、“中身のある変化” です。
まとめ
フジテレビの提訴は危機管理の一手としては理解できるものの、
「前社長らを悪者にして会社を守る」
という印象を与えやすい対応でもあります。
一時的に立場を保てても、信頼を取り戻すためには「組織としてどう変わるか」が問われるのです。
📌 次回予告
明日は、このニュースを「心理学」の視点から掘り下げます。
人はなぜ“悪者”を作りたがるのか? ― スケープゴート心理に迫ります。